【症状】
元気や食欲の減退、咳、嘔吐、血尿。時には無症状で“突然死”
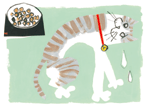
illustration:奈路道程
| 「フィラリア症」は、「犬糸状虫(フィラリア)」という、成虫になれば、そうめんのような白く細長い姿になる(メスで体長30センチ近く、オスで17〜18センチほど)寄生虫が、主に肺動脈の入り口あたりに住み着き、肺動脈を障害して、寄生した動物の命を奪いかねない病気である。 「犬糸状虫」は、その名が示すように犬によく寄生するが、犬だけでなく、症例は少ないが、猫や人、アザラシなどに寄生することもある。近年、猫に犬糸状虫が寄生して重い症状を引き起こす症例が注目されるようになってきた。もちろん、寄生の可能性は犬よりずっと少ない。しかし、注意すべきなのは、猫の場合、同じフィラリア症でも、犬の場合と違って、病気の進行、症状の現れ方が“急”なことである。 犬の場合、年ごとに寄生する親虫の数が増えていき、何年か後にはたくさん(多いと何十匹)の親虫が肺動脈に集まり、元気がなく、息を切らせたり、咳き込んだりし、放置すれば死に至る。しかし、猫の場合はわずか1匹か2匹の親虫が寄生しても元気や食欲がなくなり、咳や嘔吐などの症状が出たり、血尿が出たり、あるいはほとんど無症状のまま、突然死したりするケースが少なくない。 猫は犬より心臓などの臓器も小さく、肺動脈などの血管も細いため、万一、犬糸状虫が寄生すれば悪影響が出やすい。加えて、犬糸状虫に対する猫の免疫力の“強さ”が、かえって命を縮めると言えそうである。 |