【症状】
動作・歩行や運動の異常、長い休息時間
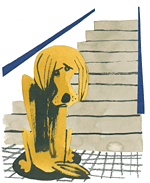
illustration:奈路道程
こんな時、ひじやひざ、前足首や後ろ足首、指関節、肩や股関節などのどこかが関節炎になっている可能性がある。
関節は、骨格のなかで、動物の体を支えながら運動機能を確保する、可動的な、独立した骨と骨との「組み合わせ部」である。だから、どこかの関節が悪くなれば、人でも動物でも、体を動かすと、違和感や痛みを感じやすくなる。人なら、「どこかおかしい、痛い」と病院通いもできる。しかし、犬が痛みで悲鳴をあげるのは、かなり重症になってから。ほとんどは、前述したような、飼い主が注意して観察しないと見過ごしかねない動作によって耐えている。また、同様な動作は神経疾患でも起こる可能性があるため、疑わしい場合は最寄りの獣医師に診てもらう必要がある。
なお、関節は構造が複雑で、具体的にどの個所が問題か理解しづらい。簡単に述べると、相対する骨の先端を覆い、衝撃を吸収し、動きをスムーズにさせるのが軟骨。全体が「関節包」という膜で包まれ、内面の滑膜から潤滑油のような関節液が分泌され、関節内部を満たす。膝関節には、骨と骨を結ぶ腱と連結し、ひざの機能と安定性を向上させるお皿(膝蓋骨)もある。