【症状】
過飲・過食、やせ、脱毛、おなかのたるみなど
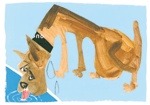
illustration:奈路道程
| 「クッシング症候群」とは耳慣れない病名だが、主に高齢期の犬がかかりやすい病気のひとつである。例えば、このごろ、愛犬がよく水を飲む。食欲もすごいのにやせだした。被毛がどんどん抜け、おなかもたるんできた。どうしたのだろうか。このような症状は、すでにこの病気がかなり進行している可能性がある。 クッシング症候群とは、日本語名で「副腎皮質機能亢進症」といわれる病気で、「副腎皮質」から「コルチゾール」という「副腎皮質ホルモン(ステロイドホルモン)」を過剰に分泌することによって起こる(「クッシング」は、この症状を発見したアメリカ人医師の名前)。なお、「副腎」とは、左右の腎臓の上端にあり、体の細胞の働きを活発にするアドレナリンやコルチゾールを分泌する、小さな器官である。アドレナリンは中心部の副腎髄質で、コルチゾールは表層部の副腎皮質でつくられる。 細胞に活力を与えるコルチゾールは、獲物を追いかけたり、敵から逃げたり、異性を求めて争ったりする、動物に不可欠なホルモンである。しかし、何らかの要因でクッシング症候群となって限度以上の分泌が続くと、前述したような症状が現れ、ついには糖尿病を併発。放置すれば死に至る。 クッシング症候群は主に6、7歳以上の犬に多いが、中には1歳未満の若い犬にも見られ、犬の品種、年齢を問わず発症する。食欲が旺盛になったりするために見逃しやすく、全身の被毛が抜けたり、異常にやせたりして驚いた飼い主が来院することが多い。 |