体の細胞が糖分を活用できなくなれば、大変
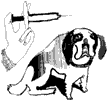
illustration:奈路道程
本来、動物の体はよくできていて、血中に含まれる余分な糖分は腎臓で回収され、再活用される。しかし血糖値が上がって、ある一定の値(動物によって多少異なり、犬はほぼ人間と同じ。ネコはそれよりも高い)を越えると、せっかく食餌から取り込んだ糖分は、活用されることもなく、尿にまじって排出される。糖尿病といわれるゆえんである。
体(の細胞)が必要とする糖分が不足すれば、食欲が異常に高まり、食べ物から糖分を取ろうとする。しかし細胞まで届かない。だから体は、自分の脂肪を活用しようとする。そのために体はどんどんとやせていく。尿の中に糖分が捨てられれば、当然水も多めに捨てられる。そうするとのどが乾き、水をガブ飲みすることになる。さらに悪いことに、自分の脂肪を活用しようとすれば、ケトンという有毒物質が血中に溶けだし、血液が酸性化する。そうなれば、吐き気や嘔吐が起こる。また血糖値が上がりっぱなしだと、血液がねばついて、いろいろな器官の血管にも影響がでる。このため肝臓や腎臓の機能が低下する場合もある。
糖尿病は、発見が遅れ、治療が手遅れになれば、一命を奪いかねない病気なのである。